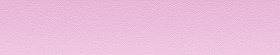NHK「ラジオ深夜便」6月2日の萩尾先生の回をテキスト化しました
2014年6月2日の深夜、萩尾望都先生がNHKラジオ第1で放送された「ラジオ深夜便」に出演されました。そのときのお話をテキスト化しましたので、アップします。テキスト化については、白峰彩子さん ( @mtblanc_a )にご協力いただきました。ありがとうございました。
アンカーの迎康子さんという方は昭和25年生まれ。つまり萩尾先生とほとんど同年代。詳しいわけです。
※ラジオ深夜便では「アンカー」という言葉を使っています→用語解説
6月3日火曜日。時刻は4時5分をすぎました。NHKラジオ深夜便今夜は遠藤ふき子がお伝えしています。
この4時台は「明日への言葉」です。今日は漫画家の萩尾望都さんに「創作の泉は尽きることなく」というテーマでお話しいただきます。萩尾望都さんは昭和24年、福岡県大牟田市で生れました。昭和44年「ルルとミミ」でデビューし、以来文学性が高い作品で少女マンガの世界の広げ、多くの読者の心をとらえてきました。代表作には「ポーの一族」「トーマの心臓」「11人いる!」「イグアナの娘」などの作品があります。平成24年には紫綬褒章を受賞しました。「少女マンガ界の偉大なる母」「少女マンガ界の至宝」とも言われています。
デビューから45年たった現在も連載をかかえ、精力的に創作活動を続けていらっしゃいます。
聞き手は迎康子アンカーです。
【迎】萩尾さん、どうぞよろしくお願いいたします。
【萩】よろしくお願いいたします。
【迎】ようこそお越しくださいました。
【萩】はい、ありがとう、はい、どうも。
【迎】金のネックレスがきらめいていらっしゃいますね。
【萩】あ、どうも、なんか。
【迎】お仕事の時はでもリラックスした...?
【萩】ほとんど、はい、もう寝間着みたいなものを着て、ああ、やっております
【迎】そして萩尾さんはデビューから45年ということで、どうでしょう、これまでを振り返って早かったかなというお気持ちですか?
【萩】いや描いている時は長いなと思ったんだけれど、振り返ると不思議なことにあっという間ですね。やっばり。はい。でも仕事を続けられてよかったなと本当につくづく思っています。はい。
 【迎】いま連載していらっしゃる作品のひとつは「王妃マルゴ」。
【迎】いま連載していらっしゃる作品のひとつは「王妃マルゴ」。
【萩】あ、はい、カトリーヌ・ド・メディシスの娘で、ちょうど16世紀のフランスが宗教の内戦に入っていた頃のお姫様なんですね。ちょっとおもしろい背景を持っているので、これを題材にマンガを描いています。
【迎】ですから、カトリックとプロテスタントの対立が激しい...。
【萩】そうですね。
【迎】そのフランスの当時...。
【萩】そう、はい。
【迎】で、このお母さんであるカトリーヌ・ド・メディシス、メディチ家からお嫁入りしてきたという。
【萩】ええ、はい。とてもおもしろいこのお母さんがキャラクターで、はい。イタリアの文化をフランスに伝えたりとか、それからご主人、王様が亡くなった後、女手ひとつで若い息子を支えて国を切り回したりとか、嫌われたり賞賛されたりとか、いろいろあるおもしろい方なんですけど、この方の本はけっこうたくさん出ているんです。やはり歴史上は重要人物なので。でもその娘のマルゴに関しては、あまり本がなくて、しかも歴史書というとけっこう男性が書かれるので、あの、なんか女の勘所みたいなものが、なかなか厚みが足りないというか。はい。それでちょっとその歴史書を読んでいるうちになんか自分なりのマルゴのイメージがだんだん湧いてきて、それで描いてみようかなと思ったんですね。
【迎】もともとそういった歴史には関心がおありだったんですか?
【萩】何かかにか好きは好きですね。で、この時代は聖バルテルミーの虐殺というカトリックとプロテスタントが争った大虐殺のエピソードが一番有名なんですけれど、やはり私もそれにすごく惹かれまして、なんでこんなことが起こったんだろうと資料をこう、だんだん調べているうちにあの背景となるキャラクター、いろんな、それこそカトリーヌ・ド・メディシスとか、それからエリザベス女王も、海の向こうのイングランドにいるんですけど、関わりますし、それからスコットランドのメアリ女王もちょっとからんでるしで、非常に人物像がたくさんあっておもしろかったんですね。
【迎】ですから同じ時代にそれこそ女性たちがいろいろな意味で活躍していたんですね。
【萩】おもしろいですね。はい。
【迎】でも萩尾さんがそういった歴史をマンガとして、しかも長編で取り上げるというのは、初めてのことだそうですね。
【萩】あ、長編は初めてですね。もうなんか苦労してます。もうどうしようという感じで。はい。
【迎】でも、かなりもう長く連載が進んでいて。
【萩】はい、だいたい3年目なんですけれども。はい。あと3年ぐらいでなんとか収まりたい。
【迎】その最初にたとえばこのくらいの期間かなというのはある程度、こう、目途というのは立てられるものなんですか?
【萩】んー、このマルゴに関してはだいたい単行本でいくと4、5冊かなという感じで始めたんですけど、まだ結婚もしていないので、単行本2冊になって、まだパルテルミーにたどりつかないので、はい、さあどうなんでしょうという感じです。
【迎】ええ。
【萩】がんばります。
【迎】それこそ、そのマルゴの母親である、このカトリーヌ・ド・メディシスも大活躍というようなことで。
【萩】そうですね。
【迎】その海の向こうのエリザベス1世であるとかメアリー・スチュワートであるとか。
【萩】いろいろ、こう、たどっていくとその頃のヨーロッパというのは何かかにかと親戚関係で、それもまたおもしろいんですね。その親戚関係になるのは結局、娘を差し出して戦争を終わらせるというところがあったんですけれど、それでその他の国とのバランスもそれでうまくとっていたところがあって、そこら辺もおもしろいです。
【迎】ただ、その実際にマンガで表現するとなると、たとえば服装があったり、その調度品はどうだったのかとか、いろいろなことに目くばりをしなければいけないから大変ですよね。
【萩】いや、そうなんですよね。もう、本当にさりげない話が......。寝るとき靴下をはいたんだろうかとか。あと、本格的にトイレというものがまだないんですよね。ちょっと、簡易トイレみたいなのがあるんですけれど。お着替えをどうしていたんだろうかとかね。そういった基本的でわかりそうで、わかんないところが、わからない。みんな知っていそうなことが、ちょっとわからない。
【迎】多分公式的な記録というのには、多分そういうのは出てこないでしょうから、そのプライベートの部分のところが、なかなかむずかしいかもしれませんね。
【萩】そうですね。いろんなエピソードはあるんですけど、そのエピソードをじーっと見ながら、窓からバケツを投げ捨てたとか。うーん、これは何のことを何のことを言っているんだろうかとかね。
【迎】まだまだでは歴史との格闘が続くということですね。
【萩】はい、行間を読みながらちょっとがんばっております。
 【迎】この展開もまた私たち楽しみにいたしておりますので。そして今、萩尾さんの代表作のひとつである「トーマの心臓」が舞台になってちょうど公演中ですね。
【迎】この展開もまた私たち楽しみにいたしておりますので。そして今、萩尾さんの代表作のひとつである「トーマの心臓」が舞台になってちょうど公演中ですね。
【萩】あ、そうなんです。スタジオライフという劇団が、今、新宿の劇場で公演しています。長くお世話になっております。
【迎】スタジオライフといいますと、男性だけの俳優のみなさんが。
【萩】そうですね、はい。
【迎】しかもいわゆるイケメンぞろいという。
【萩】はい、みなさんかっこいいです。はい。
【迎】何度も何度も萩尾さんのこの「トーマの心臓」だけではなく、他の萩尾さんの作品も舞台化していらして。
【萩】そうですね。なんか演出家の倉田さんが最初に「トーマの心臓」をマンガ作品としてはスタジオライフではじめて演出していただいて、それから何かあの、彼女は本当は文学少女で、マンガはほとんど読んだことがなかったらしいですけど、それからだんだんいろんなマンガにはまってっていうんですか、本当にいろんなマンガをスタジオライフの舞台に乗っけているようです。
【迎】この萩尾さんの「トーマの心臓」は映画でも金子修介さんが映画化していらっしゃる。
【萩】はい、かなり違うものになっておりましたが、金子さんが、はい、つくられました。
 【迎】この「トーマの心臓」というのはドイツの全寮制の男子校、まあ、中学校と高校が一緒になったような。
【迎】この「トーマの心臓」というのはドイツの全寮制の男子校、まあ、中学校と高校が一緒になったような。
【萩】そうですね。
【迎】はい、学校が舞台になっていてとにかく、こう、少年の微妙な心というんでしょうか。
【萩】思春期のなんか、こう、いろいろ、わやわやとしたものを描いております。
【迎】もともと萩尾さんが「トーマの心臓」をお描きになったのは40年も前ですか。〔注:発表は1974年〕
【萩】いや、昔ですね。本当にね。
【迎】その頃はどういうお気持ちで、この「トーマの心臓」をお描きになったんでしょうか。
【萩】これ、ドイツが舞台なんですけど、私、ヘルマン・ヘッセが大好きで、ヘルマン・ヘッセっていうのはもうちょっと本当に古い人なんですけど、その人の書いている世界観みたいなものが本当に好きで、なんかなんとなく「トーマの心臓」を描く時に舞台はドイツだし、時代、違うんですけど、ヘッセ風に、という感じで。イメージとして、気持のイメージとしてはそんな感じで描きました。
【迎】何か、こう、まっすぐな少年の心と言いますか。
【萩】いや、まっすぐになりたいと思うけれど、なれないというか。わちゃわちゃとしてしまうという。当時それから「哀しみの天使」という映画が上映されていたんですね。これはフランスの映画で、ディディエ・オードパンという少年が主人公で、パリの寄宿舎の話で、そういったほのかな初恋の物語。これにやっぱり非常に影響されまして。ああ、なんか学校を舞台にしたお話を描きたいなと。あの、学校とか、それからちょっと極端ですけれど刑務所とか、なんかこう集団で過ごす場所、一種閉鎖空間というんですか、はい、なんかその中ではいろんな関係性がどうしても濃密になっていくから、おもしろいなと思って、それでそういう題材になってしまいました。
【迎】でも、自分を追及するというんでしょうかね、自分はいったいなんなのかと、なぜ生まれてきたのか。ええ、やっぱり傷つきやすいところもあったり。
【萩】まあ、そうですね。
【迎】ただ、あれだけ長く連載した「トーマの心臓」がかなりコンパクトな舞台になっていて、実に見事に。
【萩】そうですね。倉田さんが本当にきちんとまとめてくださって、なんか最初に脚本におこした時には4時間以上になって、あれをカットして、これをカットしてとかいって大変だったと伺いました。なんかすごく熱心につくっていただきました。
【迎】そして演じている俳優のみなさんも萩尾さんのマンガの中で、たとえばどういうポーズをとっているのかとか、どういう表情なのかとか。
【萩】心理をさぐるのに、とにかく倉田さんから「マンガを読むように」って言われて、それで読んでいるとやっぱり絵が目に入ってくるものですから、それでみなさん思わずマンガから抜け出たような。なんかデジャブという感じで舞台に絵が広がっていきます。
【迎】私も先日拝見しましたが、10代と思われる若い女性からそれこそ私と同じくらいの人まで。で、だいたい女性で。ま、男性がチラホラといた雰囲気で。ですからおそらく後から萩尾さんのマンガで「トーマの心臓」を読むという方も、若い女性たちの中にはいらっしゃるのかな、と思ったんですね。
【萩】あ、ありがたいことですね。はい。ぜひ読んでください。
【迎】ですから、それこそそういうふうにして読み継がれていく、伝えられていくという世界があるんだな、と。
【萩】はい、読み継がれていっていただけると、もう作者冥利に尽きますね。
【迎】と言う「トーマの心臓」ですけれども、萩尾さんご自身は小さいころはどんなお嬢さんだったんでしょうか。
【萩】うーん、どんなでしょう?...だったんでしょうね。いや、まあ、やはり絵を描くのが非常に好きで、絶えず紙をもらっては絵を描いていた、絵やそれからマンガ。はい。えんぴつ描きですけれども。子供のころ誰でもお絵描きとかいたずら描きとかするから、その延長なんですけど、私の場合はそれがえんえん続いて漫画家になってしまったという感じです。
【迎】はい、ただ。だいたい私も同じような年代なんですけれども、なかなかマンガを買うおこずかいは親はくれなくて。友達から貸してもらったりとか。
【萩】ええ、そうですね。はい。私もそうで、学級文庫じゃないんだけど、学級の文庫の中に何冊かやっぱりみんなが家から持ってきた古いマンガがあったりするんです。それから近所のお家に読ませてもらいに行ったりとか、床屋さんにあったりとか、何かかにかそんなふうにして当時のマンガを読んでいました。
【迎】やはり萩尾さんも家ではあまりマンガは読んじゃいけないというようなことはあったんでしょうか?
【萩】あの、親が許可したらいい、と。
【迎】基本はダメと?(笑)
【萩】だからすごくいい子にして、学校の成績良くして、お手伝いして......「お母さんこの本読んでいい?」とか言って友達から借りてきたものを読ませてもらうんです。ダメな場合には公園かなんかに行ってこっそり読んで(笑)。
【迎】(笑)。なんでしょうね。何か、こうマンガはあまり...。
【萩】そうです。
【迎】大人にはよく思われてなかったですね。
【萩】あ、ま、完全にそうですね。手塚先生自体が新しい文化を切り拓かれた、マンガの新しい文化を切り拓かれた人だから。本当にマンガ読まないで育った世代の人には、マンガはつまらないものという考え方が本当に固定化されていて、「そんなつまらないものをいつまでも読んでいる」というところからぜんぜん発想が抜けないみたいですね。で、コマっていうのはひとつずつ読んでいくんですけれども、読むのにもちょっとスキルがいって、この読むというがなかなかやっぱり慣れていないと大変。
【迎】そうしますと、萩尾さんが漫画家になって、でもご両親は漫画家という職業についてはどういうようなイメージを抱いていらしたのでしょうか。
【萩】なんか単に私がなりたがっているだけで、一応許可したけれど、1年か2年でやめて帰ってくるだろうと思っていたみたいですね。それで、ですから、当時は女の人は結婚して仕事をやめて家に入らなければという概念が非常に強かった時代なので、会う度に、漫画家になってからも会う度に「早く結婚しなさい」「いつ仕事やめるの」とかね。仕事というのが仕事という概念は親にはないんですね。たしか。絵の塾みたいなものをやっていると思っている。はい。
【迎】じゃ、実際にあまり手にとってご両親は萩尾さんのマンガをお読みになるっていうことは?
【萩】なんか時々は読んでたらしいですけど、理解していただいたのかどうかよくわからないです。はい。
【迎】でも、紫綬褒章ということで、きっと大変なことをなさったとご両親も思われたんじゃないでしょうか?
【萩】なんかね、それと作品をどう捉えるかというのは、どうも分離しているらしくって、なんかつながらないみたいですね。
【迎】ああ、じゃあ、賞をとったということは、きっと大変なことで。
【萩】きっと喜んでくださっているんですけど。
【迎】お喜びになるけれど、それとその萩尾さんの作品世界とは結びついてない。
【萩】それはちょっと。はい。母がなんていうのか、私がお絵描き教室ではなく仕事をしているんだとわかったと言いだしたのはNHKでやっていた「ゲゲゲの女房」、あれを見ていてわかったらしいんです。
【迎】あ、水木しげるさんがあの朝のドラマのモデルですから。
【萩】そう。モデルで、それでずーっと仕事をしているのを見ていて。で「お母さんは知らんかったたい」って電話で言ってきたんです。「え、なに?」なんて言ってたら「水木さんがね、一生懸命、仕事、マンガ描きおったたい」「なんかいろいろ悩みおったたい」って。
【迎】(笑)
【萩】私もそうなんですけどって。なんかそこら辺ぜんぜんつながっていなかったみたい。
【迎】だからマンガを描くということは仕事というイメージにはなっていないということですね。
【萩】なってない。本当に何かつまらないものを勝手にやっているという感じだったんですね。
【迎】でもきっと今は、いろんな理解がお母様にもおありなのではないかと思いますが。
【萩】とりあえず、あの、「ゲゲゲの女房」くらいのところまでは理解していただいている。はい。
【迎】そして萩尾さんの作品といいますと、本当にいろいろな要素があって、SFであったりファンタジーであったり。ただ、舞台はそれこそ海外、日本以外のところを舞台にした作品というのが。
【萩】大半がそうですね。
【迎】それは何か理由があるんですか?
【萩】ひとつにはちょうど子供時代にアメリカ文化の影響を非常に受けたんですね。主にテレビドラマと時々やってくるディズニーの映画ですけれど。それで非常にアメリカ文化の世界というのがおもしろくて。台所に巨大な冷蔵庫があったり。そちらへの好奇心から海外を舞台にした作品がやっぱり多くなってしまいました。ま、SFが好きだったり、ヘッセが好きだったりとか、そういうのもあるんですけれども。あと、日本を舞台にしてものを考えようとすると、どうしても家族関係について、マンガの中に描かなきゃいけない。で、家族関係というと、どうしても自分の家族関係がモデルなってしまいますから、ちょっとそれを描くのがつらくて。で、ちょっとなるべく日本から逃げていました。
 【迎】あの「11人いる!」という作品があって、それはそれこそ宇宙でテストを受けるという。もう宇宙が舞台という。
【迎】あの「11人いる!」という作品があって、それはそれこそ宇宙でテストを受けるという。もう宇宙が舞台という。
【萩】そうですね。宇宙船の中で大学入試のテストを受けるという、そういうお話ですね。10人集まって1チームのはずなんだけど、フタを開けてみたらひとり多くて11人いる。誰かひとり受験生じゃないのが混ざっている、誰だ?......となんかそういう話です。
【迎】だからそれぞれが疑心暗鬼になって、いったい本物の受験生でないのは誰だ?というような。でもその参加している受験生がさまざまな星から来ているので、もういろんな皮膚を持っていたり、ちょっと顔かたちも違っていたりという。あの発想もまたびっくりなんですけれども。
【萩】ありがとうございます。でも地球人は、というとあれですけれど。まあSFの世界は結構本当に宇宙人にあこがれていて、ウェルズとかヴェルヌの時代から「月世界旅行」とか「火星探検」〔注:ブラッドベリの「火星年代記」のことか?ウェルズの「宇宙戦争」のことか?〕とかいろんなSFの古典があるんですね。そこにはやっぱり不思議な月世界人とかね、タコのような火星人とかね、いろいろ出てきますから。本当にひとりひとりこういう宇宙人がいたらっていうキャラクターを考えるのがとてもおもしろかったです。
【迎】それはもう別に、考えるといろいろな発想で出てくるんですか?
【萩】あ、そうですね。はい。
【迎】そしてまた子供のころは男性でもなく女性でもなく。で、ある程度の年齢になった時に選択して、男性になるか女性になるか道が決まるという設定の受験生もいましたね。
【萩】そうですね。未分化の。何か生物学で性が変換していく魚とかカタツムリとか、そういうのがあったので、その時は「ああ、おもしろいな」ぐらいな感じで、そういった生物学の本を読んでいたんです。けれど、実際にSFの世界にはちょこちょこそういう発想が入り込んでいて、特に文化的に、人種と文化を一緒にしてアーシュラ・K・ル=グウィンという人が「闇の左手」という物語を書いたんですね。で、この星に住んでいる人がやはり成長期に性転換をする。普段はなんかどちらでもない状態で。これを読んだ時に「これはおもしろいな」と思って。で、それに影響されまして。はい。ずっと未分化のままきてある一定の、思春期になったら男か女に性を選択するというキャラクターを作ったんですけど、そのキャラクターを考えている時はものすごくおもしろくって。というのは、女の子は小さい時から女の子らしくしなさいって、一種、ワクに収められてしまうんですよね。で、自分の個性として、ほかにいろんなものがあるにしても女の子はそんなことはしません、木登りとかね、大声で騒いだりしません、廊下は走りませんって感じで。おてんばっていうのでひとくくりにされたりして、なんか非常に不自由を感じていながら「いや、私は女の子なんだからそうしなきゃいけないんだ」と自分で自分を抑圧していたところがずいぶんあるんですけれど。「11人いる!!」に出てくるフロルはまだ男でも女でもないんだから何をやっても「女の子だから」って言われないですむ。「いいな」と自分であこがれながら描きました。
【迎】ですからいろいろお読みになった本であるとか、たとえば萩尾さんの子供時代だとか、様々なものがそういうひとつの作品の中で生かされている。
【萩】そうですね。
 【迎】そして、テレビドラマにもなった「イグアナの娘」。これは、一応舞台は日本のごく普通の家庭。
【迎】そして、テレビドラマにもなった「イグアナの娘」。これは、一応舞台は日本のごく普通の家庭。
【萩】そうですね。
【迎】なんですけれども。母親との関係で、どうしても自分の娘がイグアナに見えてしまうという。
【萩】そう、お母さんがね、子供を産んでみたらイグアナだったと。おっきなトカゲですよね。そのお母さんは娘がどうしてもどうしても愛せないんですね。ま、そういうお話で、テレビのドラマにもしていただきました。菅野美穂ちゃんがね。
【迎】そうですね。菅野美穂さんがそのお嬢さん、イグアナに見えてしまうというお嬢さんの役で、お母様の役は川島なお美さんが。
【萩】そうですね、
【迎】多分テレビでご覧になった方もたくさんいらっしゃるかと思うんですが、これは何か不思議な発想のマンガだなと思って。
【萩】いや、いえ、そうですね。ちょっと両親との間にずいぶん私は葛藤があったので、何とか理解してもらいたいと思って、いろんな話もしますし、したし、説明もしたんですけれども、あの、どうしてもすれちがってしまう。だもんでその時期は心理学書なんかたくさん読んだりして「どう言えばいいんだろう」「どう言えば伝わるんだろう」とちょっと考えていたんですけれど、そのうちに「こんなに言っていることが理解してもらえないということは私はもしかしたら人間じゃのないかもしれない」。で、ふとその当時見ていたテレビでガラパゴスのイグアナの特集をやっていたんですね。で、イグアナっていうのはおもしろいことに人間の胎児に似ているんです。まあ、トカゲ類は尾っぽがあって、口が横に広くて、目が顔の左右についていて。そのガラパゴスのイグアナが海を見てね、なんかこう「あー、本当は人間に生まれたかったな」と言ってるように、ちょっと思えちゃったんです。単なる想像ですけど。それで「そうか、人間じゃなくて私、イグアナかもしれない。それで親に理解してもらえないんじゃないかしら。」と思ったら、その「イグアナの娘」のアイデアが出てきて、ちょっと思いついたらおもしろかったので描いてしまいました。
【迎】やっぱり母親というのは、何かこうあって欲しい自分の娘に対するイメージみたいなものもあるし。
【萩】そうですね。決してその何ていうのかな、これが娘の幸福だというものを信じていて、だから幸福になって欲しいからいろいろ言うんですよね。だけど娘から見ると大迷惑。申し訳ないけど、それはちょっと、それねえ二十歳くらいまででちょっといい加減おさめてくれる?という感じで。もう見守る時期にして欲しいという。だから「お前のために言っている」というのもわかるけれど、逆にそれが強いと支配しているということになってしまいますし、なかなかちょっと、両方で相容れなくてつらいものがありますね。
【迎】でも家族ということは、どうしたってそこを切り離す訳にもいかないというところが、なかなか難しいですよね。
【萩】そうですね。他人だったらつきあわないような人でも、家族だったらつきあわないといけないですもんね。
【迎】そうですか。ですからやはり萩尾さんの様々な、不思議なといいますか、大胆の極みのような作品もいろいろなところに、こう、いろんなヒントが散りばめられているんですね。
【萩】はい。
【迎】でも、別にそれは考えていることがあってパッと作品になるのか? こういうテーマはどうかと思うところにいろいろこれまでの、たとえば蓄積しているものが結びつくのか?
【萩】多分、両方なんじゃないかと思うんです。思ってもみなかったところから降ってくる場合もあるし、なんか気になることがあって、ちょっとこれはいつか形にしたいなと思いながら、いろんなピースを寄せ集めているうちに「あ、できた」とある時、何か最後のひとつが結びついてできあがったり。それは本当にいろいろですね。何かその、現実の世界にちゃんと生きているつもりでいるんですけれど、何かそれ以外にもこの現実以外にもいろいろあるんじゃないか、私たちが知らされている、毎日接している世界のほかにも何かあるんじゃないか。それは幻想のことでもいいし、もしくは歴史上の隠された秘密でもいいし。何だかついついそういうことを考えてしまうんですね。それというのはつまり現実が生きづらいんですね。きっと、私は。ちょっとそちらのサイドを考えている方が過ごしやすいんじゃないかなと思います。ついつい考えてしまう。
【迎】今、目の前にある現実のほかに、もしかしたら普段見られない別の真実と言いますか、現実があるかもしれない。でもそういうふうにして暖めていて、かなり時間が経ってからひとつの作品になって、形になるという場合もあるんでしょうか。
【萩】そうですね。それはあります。もちろん構築されないまま、なんか沈んじゃうのもあるし、どっかに逃げてしまうのもあるし、それは本当にいろいろです。
【迎】たとえば、お描きになっていて内容が変わってきたりとか、思いがけない展開になるということもあるんですか?
【萩】あ、ありますね。なんかだいたいマンガはキャラクターなんですけど、キャラクターと対話をしながら作っていくんです。だから自分がキャラクターに身近であればあるほどキャラクターがいろんなことをしゃべってくれる。そうするとキャラクターっていうのは自分の内面心理の現れですから、自分が本当はもうちょっとカッコつけていきたいなと思っていたり、ここらへんは見たくないと思っていたものをキャラクターが言いだしてくれたりするんですね。「本当はこうなんでしょ?」と。「げげ。なんで知っているの?」「ちょっと隠してこっそり生きてきたのに」。でも、それはそれでまたちょっとおもしろい。
 【迎】そうしますと、たとえば今、連載していらっしゃる「王妃マルゴ」があって、マルゴならマルゴの絵を描いている時、話しかけたり。
【迎】そうしますと、たとえば今、連載していらっしゃる「王妃マルゴ」があって、マルゴならマルゴの絵を描いている時、話しかけたり。
【萩】あ、それかもしくはストーリーの構想をしている時にマルゴのキャラクターのシーンを考えていると、いろんなことを言いだす。はい。そこにはカトリーヌ・ド・メディシスがいて、お兄さんのシャルル国王がいて、それから王位をねらっている弟がいて、という感じで。みんな勝手なことをしゃべっています。
【迎】だから、それはちゃんとひとつの人格となってもう動いている。
【萩】そうですね。キャラクターがわからないと表情が描けないので。
【迎】今お描きになる時間というのは1日の中のどういう時間をお使いなんですか?
【萩】だいたいお昼すぎから明け方までです。
【迎】だから夜更かしをなさって仕事を。
【萩】そうですね。
【迎】で、何枚描かなければとなったら、その何枚きっちり仕上げるまではなさると?
【萩】いや、このごろ本当に筋力が衰えて、いや今なんかパワースーツとかリハビリ用にいろんなスーツが考案されていますけど、本当にああいうのが早く大量生産されないかなと。ハイブリッド腕とかハイブリッド肩掛けとかハイブリッド手袋とか。
【迎】あの線の、描かれている1本1本が本当に線が細やかで、ですから手作業としても実に厳しいものなんですね。
【萩】歳を...歳は本当に、歳をとると筋力が...この話ばっかり(笑)...衰えますから、本当に線1本を出すのが大変になってくる。だから若いころは、本当に今思うとぜいたくに線を出してたな、と。自由自在だったから。今はこういうイメージの線を出したいというと、なんかもう必死で息をつめて描かないと出ないという。よれるという。
【迎】じゃあ、スッと引けたら爽快ですね。
【萩】もう爽快ですね。はい。みなさん、仕事は若いうちにやりましょう。体力のあるうちに。
【迎】でもアイデアはもう次々とそんなふうにして。
【萩】あ、アイデアはあまり変わりなく出てきます。
【迎】で、しかも、たとえば「王妃マルゴ」を描きながらいろいろまだ暖めている世界がいくつもあり。
【萩】あ、ちょっと卵のように暖めて。はい。
【迎】素晴らしいですね。
【萩】いえね、創作は業だと言いますけれども、多分何かあるんでしょうね。
【迎】あくなき追求ですね。
【萩】はい、そうですね。
【迎】でも、それこそ今はマンガが日本の文化、アニメも含めてですけれども、日本の文化としてたとえばひとつのミュージアムであるとか記念館であるとか、そういう時代になってきたなという気もするんですけれども。
【萩】そうですね。本当に1990年代の後半から流れがそうんなふうになってきて、なんかポジションが本当に変わりました。本当にびっくりしました。海外でもいろんなマンガのフェスティバルを、あちらでもこちらでもやっているようですし。本当に日本のマンガが世界中に愛されて、本当にうれしいかぎりです。
【迎】実際にそういった世界のフェスティバルにいらしたりという機会はおありなんですか?
【萩】パリとアメリカのサンディエゴのフェスティバルに行ったことがあるんですけれども。
【迎】どんな様子でした?
【萩】まず、むこうの人に聞くと、日本のアニメーションを見ていって、マンガにハマった。だからそれこそ「うる星やつら」とかいろんなそういったアニメーションで。「じゃあサザエさんは?」と言ったらそれはあんまりコアらしくて、なくて、むしろ青春冒険物ですか。でも、それでマンガを読むようになって、最初は逆版で読んでいたの、あの横文字は、フランス語もドイツ語も。
【迎】ギャクハン?
【萩】はい。つまりページの開きが逆ですから。本は。ところが最近では日本のマンガっていうと逆開き(アキ)じゃなくても普通の日本のマンガのように。
【迎】だからページを開ける時、私たちは左から右へめくっていくのが、海外の方は逆に。
【萩】英語の教科書みたいに読んでいたんですけれど、今では国語の教科書のように、そのまま読んでくださっている。それくらい浸透しているし、駅のキオスクとかコンビニで売っているんです。マンガが。翻訳されたものが。スゴイなと思います。
【迎】萩尾さんのマンガを読んでいらっしゃるヨーロッパの人やアメリカの人は?
【萩】いや、そこはまだちょっとまだ知らない。
【迎】あ、そうなんですか。
【萩】これから多分やってくれるといいなと。基本アニメーションになった冒険物が主流なので。「キャンディ♥キャンディ」なんかもすごい評判で、喜ばれたみたいですね。
【迎】あのストーリーがやはり素晴らしいというふうにおっしゃるヨーロッパの人が多いですね。
【萩】ああ、はい。時々伺います。で、日本のそういったマンガ文化というのは戦後始まって、今ちょうど世界に抜きんでているので、私の考えではがんばって今のうちに売ろうと。それがいいんじゃないかなと思います。貿易の面でもそれでずいぶん黒字になるんじゃないでしょうか(笑)。
【迎】だから日本のマンガを通した文化の研究をしたいという人も、ヨーロッパでもずいぶんいらっしゃるようだし。
【萩】そうですね。カルチャーとしても十分に研究のしごたえのある文化じゃないかなと思います。おもしろいです。
【迎】だから私たちがマンガを読むのに苦労した時代とずいぶん変わってきましたね。
【萩】あ、それは読むのをやめなさいと言われて苦労した時代ってことですね。はい。そうですね、本当にお墨付きをもらえるとこんなに違うのか、と。
【迎】でも、次々と発想はまだまだ浮かんでということですから、まだ次なる作品を拝見するのも私たち心待ちにしておりますので。
【萩】ありがとうございます。体力が許すかぎり。
【迎】今日はありがとうございました。
【萩】ありがとうございました。