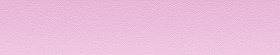「トーマの心臓 Lost Heart for Thoma」森博嗣(読了)
「萩尾望都作品目録」としてはこの作品、「カバー表紙・挿絵」にしか分類できません。
だけど、ちゃんと読んだのだから、何か書かないともったいない。
決して原作ぶちこわしな感じではない。萩尾先生ご自身が表紙や挿絵を描かれているのだから、それは当然か。でも、まぁ、先生からしたら、もう遠い過去作品だから、孫のようにいとおしいけれど、余計なお節介はかかない方がいいかしら、くらいの距離感なのかもしれないなーなんて思ったりもする。
小説だからよかったと正直思う。実写映画、舞台などだったら見なかったかもしれない。がっかりしたくなかったから。
設定の微妙な変更にどんな意味があったのだろう。
・舞台をドイツから日本に変更したこと。
・時代的には戦後のドイツから戦前、おそらく大正~昭和初期に変更したこと
・登場人物の年齢をもう3~4歳引き上げ、17~18歳くらいにしたこと
→にもかかわらず、名前をオスカー以外あだなということにして、ユーリだエーリクだとして変更しなかった。
そこにどんなねらいがあったのか。おそらくは森氏の「自分の世界」を構築するために必要な舞台変更だったのだろう。設定変更そのものは良いとしても、名前が不自然さを感じずにはいられない。いっそのこと「透馬」や「祐理」とかにしてくれた方がまだましだったかも。
小説はオスカーの一人称になっているが、原作もオスカーは一種の狂言回しで、オスカー視点の部分も多いため、それだけでは大きな変更点とは言えまい。そうではなく、完全にこれがオスカーの物語になっているところが最大の違いだと思う。原作はユーリの再生への物語だし、エーリクもトーマもそれを助ける存在で、オスカーはそれらをすべてつなげる役回りだ。
オスカーが「ユーリに何があったのか知らなかった」ということが設定の実のある変更点だ。だからユーリが何故変わってしまったのか、をオスカーが探る物語になっている。
そうして、オスカーが探っていった到着地点はユーリの秘密ではなく、ワーグナー教授との対話にあった。原作の「こんちくしょうと思っている...と思っていたんだがな」で始まるオスカーのユーリへの告白シーンがなく、ワーグナー教授=ミューラー校長への告白シーンに入れ替わっているところだ。だから、「憎しみの根源なんて...」という言葉を森氏はもっと明確に表現している。何故オスカーが校長を許せたのか。ポイントはそこじゃないかと思う。オスカーの母親のことがあまり詳しくは出てこない。(それは「トーマの心臓」もそうで、我々は「訪問者」で彼女の実像を知ることになる)。母親が優しい人だったから、彼女を愛した人だから、ワーグナー先生を憎んでいない、という点。ここはエーリクが義父を受け入れるシーンにも通じている(「二人ともマリエを愛していた。だから一緒に暮らせないかね」)
大塚英志ではないが、「母性への完全肯定をしないところ」が萩尾先生の作品の一つの大きな特徴であるならば、森氏は更にそれをもっと強く押し出したようにも思われる。オスカーの父親は結果的に妻が「自分のものであることを示すために」殺したとワーグナー教授は語る。そんな父親を恨んだこともあったが、今は好きだと語る、オスカー。
なら「ママを返して!」と叫んだ「訪問者」のオスカーはどこへ行けばいいのだろう。
グスターフのヘラへの愛情はただのエゴだと「訪問者」では感じられたし、グスターフはうっかりヘラを殺したことになっていたから、まだ彼への理解が持てた。森氏のグスターフもオスカーもここでは大きく原作を離れて、男の理屈になっている気がする。何があっても小さい子供から母親を奪うようなことはすべきではない。グスターフはヘラを殺すくらい苦しかったのなら、自分が死ぬべきだったのだと、私は思う。オスカーもそうやってグスターフを責めて良いのだ。だが、それでは自分がいつまでも苦しい。だから二人の父親を許す、と。
許すなよ、おい。
原作をおとしめるようなことはないし、別段がっかりはしないが、日本人の男の書く小説って、だからキライ。普段絶対読まなくて正解だなー。と一刀両断して、終わり。